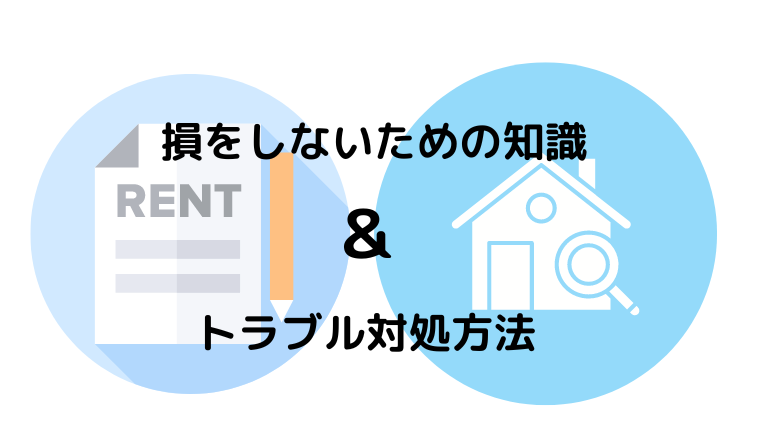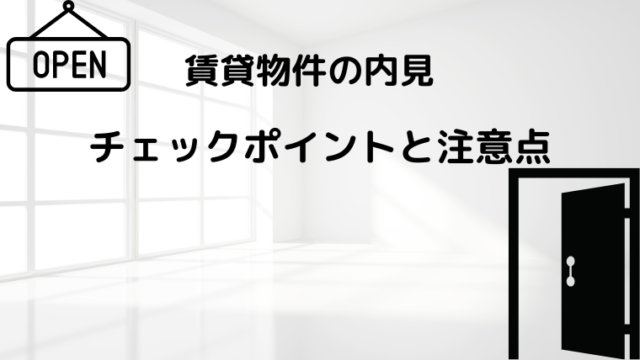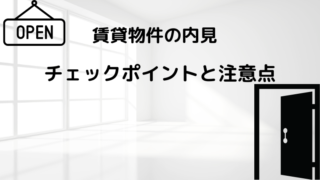- 敷金が返金されない
- 退去精算書の見方がわからない
- 退去費用に納得いかない
退去精算書が作成されても、内訳がおかしい可能性があります。疑問を感じながら、支払う必要はありません。
なぜなら、ぼったくり請求書を送ってくることがあるからです。水増し請求や架空請求もありなのが、不動産業界です。おかしい場合は迷わずに、抗議しましょう。
この記事を読めば、損をしないで退去手続きができます。トラブルになったときの対処方法が見つかります。
不当な請求額であることを見抜く知識があれば、ぼったくりは阻止できます。不動産会社に騙されない知識はあなたの心強い財産になります。
納得できない退去精算書が届いたら?管理会社に抗議する!

退去精算書が届いたら、内訳を確認してください。
そもそも内訳がなく、一式で請求されている場合は内訳を出してもらいましょう。
次に、二重に請求されていないかを確認します。
入居時に支払った鍵交換代やハウスクリーニング代が、退去時にも請求されていることがあります。
不当な退去精算書の例
退去精算書のチェックポイント
- 本当に入居者負担になるのか
- 単価の相場は適切か
- 残存年数は考慮されているか
①~⑤の例は、不当な請求書と判断できますので、管理会社に抗議します。やりとりの履歴が残るメールか、電話の場合は録音しておきます。
電話1本で、大幅に減額されるケースも多々あります。「払ってくれたらラッキー」的な感覚で請求してくる業者がいます。こちらに知識があることがわかれば、請求をすぐに取り下げるケースが多々あります。
少しでも疑問に思う点は聞いてみましょう!
①畳(1畳)についたキズに6万円(6畳)の請求
居住年数:4年
退去立会いでは、畳に家具を引きずったキズを指摘された。
このケースでは、入居者の過失によるキズなので、原状回復費用は入居者負担となります。
支払う費用は、キズがついた1畳分の負担。畳表(1畳)の相場は4,000円前後です。
6畳のうち、1畳だけ新品だと色が合わないと言われても、1畳分の負担になります。
残り5畳は、オーナー側の負担になります。
②8畳ほどのワンルームのクロス張替えに100㎡の請求
居住年数:7年
退去立会いでは、クロスについての指摘なし。実際、目立ったキズや汚れなし。
このケースでは、入居者の過失でなければ、原状回復費用はオーナー側の負担になります。
仮に、入居者に過失があったとしても、入居期間が7年であれば負担はありません。
さらに、ワンルーム全てのクロスを張替えても、10㎡ほどです。100㎡はありえません。
③クロスの張替え単価1,500円で請求
居住年数:3年
退去立会いでは、結露の放置で発生したクロスの黒カビを指摘された。
このケースでは、入居者の過失によるカビの発生なので、入居者負担になります。
ただし、クロスの単価相場は700~1,000円です。高級なクロスを使用したというより、管理会社が中抜きしている可能性が高いです。
クロスの耐用年数は6年です。残存年数が考慮されているかの確認も必要です。張替え範囲の㎡も確認。
④ハウスクリーニング代として20万円請求
居住年数:2年
退去立会いでは、目立ったキズや汚れの指摘なし。
このケースでは、20万円は暴利的な金額と判断されます。仮に、特約にハウスクリーニング代は入居者負担と盛り込まれていても、暴利的な金額を支払う必要はありません。ワンルームや1Kのハウスクリーニング費用は2~3万円です。
⑤エアコン清掃代として2万円請求
居住年数:2年
退去立会いでは、目立ったキズや汚れの指摘なし。
このケースでは、エアコン清掃代は次に住む人のための費用なので、原則オーナー側の負担になります。
【重要事項説明書の特約事項】全てが有効ではない!

退去請求書の内容に不満があるけど、重要事項説明書の特約事項に記載があると支払わなければならないのか?
重要事項説明書の特約に記載があっても諦める必要はありません。
最高裁平成17年12月16日判決(最高裁判所裁判集民事218号1239
敷金返還訴訟における「原状回復特約」について最高裁の判断
・特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在すること
・賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
・賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
要約すると、
- 具体的な金額が書かれていること
- 契約者はキチンと内容を理解していること
- 特約ページ自体に記名、捺印があること
2020年に民法改正「賃貸借契約に関するルールの見直し」でどう変わる?より入居者側の権利が守られる

なぜ、原状回復をめぐるトラブルが起こるのか?
それは、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が法律ではないからです。
ガイドラインには法的拘束力はないため、オーナー側と入居者側に原状回復や敷金に対する認識のずれが、トラブルの原因と考えられます。
そこで、2020年の民法改正により、以下のように定義されました。
2020年4月1日以降に契約締結する賃貸借契約が対象。
(賃借人の原状回復義務)
第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(敷金)
第四款
第622条の2
1.賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2.賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
この改正では,契約に関するルールを中心に,民法の債権関係の分野について全般的な
見直しがされています。
改正に伴い、ポイントを解説したパンフレットが賃貸借契約に関するルールの見直しです。
・賃借人は通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてまで原状回復の義務を負わない
・敷金は賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならない
他にも、借地借家法、消費者契約法は、情報の質・量や交渉力に格差がある弱い立場の消費者(借主)の利益を守ってくれます。
合意できない場合の対処方法は?専門家に相談する
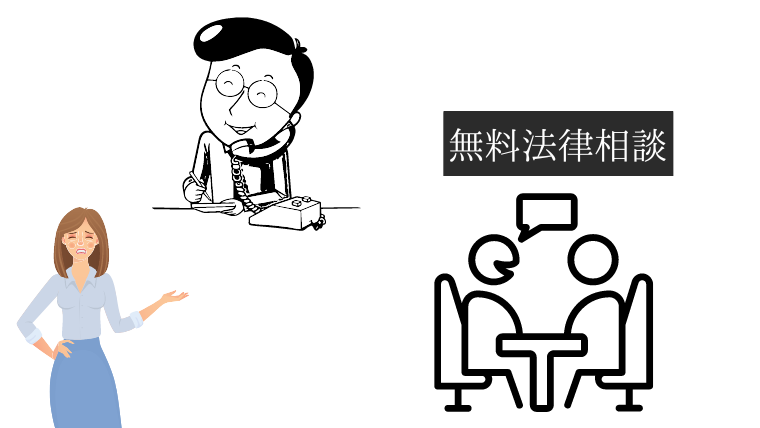
やりとりを重ねても合意に至らない場合、裁判という方法があります。しかし、費用と時間がかかるので、オススメしません。
ここでは、無料で解決する方法を解説します。
自治体の無料法律相談を利用する
お住まいの自治体が設けている弁護士による無料法律相談。お住まいの市役所(区役所)のHPで、相談開催日と予約方法が調べられます。
無料法律相談のメリット
- 契約書類と退去精算書を持参すれば、細かい説明が不要
- 電話と違い、聞き違いや説明不足がおこらない
- 対面で弁護士にアドバイスをもらえる
無料法律相談のデメリット
- 開催日が月2回や週1回であることが多く、タイミングが合わない場合がある
- 取りたい日に予約が取れない場合がある
ピロコの友人は請求額を払わないなら裁判を起こすと脅されました。無料法律相談で弁護士に退去精算書を見せたら「全ての項目、払う必要なし」と言われました。弁護士のアドバイスとおりに抗議したところ、敷金は全額返金されました。
無料電話相談を利用する
前述のとおり、敷金のトラブルは非常に多いため、無料の相談窓口が用意されています。
※相談は無料ですが、通話料はかかります
| 消費生活センター・国民生活センター 消費者ホットライン | 電話番号:188 受付時間:地域によって異なる |
| 公益社団法人 日本賃貸住宅管理業協会 | 電話番号:03-6265-1555 平日10時から17時 |
| 法テラス・サポートダイヤル | 電話番号:0570-078374 平日9時から21時、土曜日9時から17時 |
無料電話相談のメリット
- 自分の空き時間に利用できる
- 対面が苦手な人は利用しやすい
無料電話相談のデメリット
- 引越しシーズンは電話がつながりにくい
- 電話では説明不足や聞き違いがおこる可能性がある
まとめ

退去精算書が届いたら、精査することが重要です。支払わなくてもいい費用、不当に高額請求されていることを見抜く知識があれば、損はしません。
法律はあなたを守ってくれます。
交渉がうまくいかない場合は。迷わず専門機関に相談することをオススメします。